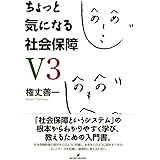無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

いま、知らないと絶対損する年金50問50答 (文春新書) 新書 – 2011/4/19
太田 啓之
(著)
保険料未納で年金は破綻しない? メディアの大誤報のせいで混乱する一方の年金問題。朝日新聞のスペシャリストがわかりやすく指南
- ISBN-104166608029
- ISBN-13978-4166608027
- 出版社文藝春秋
- 発売日2011/4/19
- 言語日本語
- 本の長さ320ページ
この商品を買った人はこんな商品も買っています
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
登録情報
- 出版社 : 文藝春秋 (2011/4/19)
- 発売日 : 2011/4/19
- 言語 : 日本語
- 新書 : 320ページ
- ISBN-10 : 4166608029
- ISBN-13 : 978-4166608027
- Amazon 売れ筋ランキング: - 493,936位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 949位文春新書
- カスタマーレビュー:
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2015年9月2日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
非常に分かり易い文章で、期待した以上の読み応えのある本です。とても参考になりました。
2012年11月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
今の年金とは 高齢者をその社会でどう支えるか という仕組みである、各自が積み立てる方式ではインフレには勝てないという点には納得しました。
2015年11月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
内容が古かった。仕方がありませんが、知識としては有りがたかった、でした。
2011年12月21日に日本でレビュー済み
年金といえば破綻する破綻するとさんざ言われていますが、
どうして破綻するのか、いまいちピンと来ませんでした。
基本的な部分の説明が足りず、どうにも理論が飛躍しすぎている感じを受けることが多かったので。
でも、ここに書かれている内容は納得できます。
なるべく易しく書こう、という意図がはっきりと分かり、
そのとおり易しい言葉で書かれていると思います。
自分の知ってたことは足りない上に間違ってた事を思い知らされました。
下手に細かいコトを覚えようとするよりは、
まずこういうふうに理解すればよかったんだな、と感心しました。
入門書とはかくあるべき、と思いましたね。
お陰で、今までは得も言われぬ不安にないなまれていましたが、
この本の内容を読み返すことで、
「問題点はこういうところにあるんじゃないか」
と理解できた気がしますし、
「まだ慌てる時間じゃない。今のうちにしっかりと舵を切り直せばいいんだ」
と思えるようになりました。
気を付けたいのは、なにもこの本は、
絶対破綻なんて気のせいだ!年金最高!
と【言っているのではない】ことでしょうか。
年金擁護がどうのこうのという評もあるようですがそうではなく、
下手な情報に振り回される前に「年金とははどういうものなのか」を理解して欲しい、
という、他の著書ではおざなりになりがちなポイントにフォーカスされています。
今抱えている問題点や、それに対する議論などもある程度拾われています。
そして、どういう制度であるのかをしっかりと解説した上で、
「今すぐにも崩壊するみたいに言われるのかおかしいと思います」
と持論を展開していらっしゃる。
まずは、年金とはどういう制度なのかを理解する参考書として、
一度目を通してみるのは悪く無いと思います。
その上で他の本を読むなり何なりしてみればいいのではないでしょうか。
私は、年金というややこしそうな事を十分易しく書いてある事、
どんな問題点を抱えているかも包み隠さず書いている事、
この2点を評価して☆5つとしました。
どうして破綻するのか、いまいちピンと来ませんでした。
基本的な部分の説明が足りず、どうにも理論が飛躍しすぎている感じを受けることが多かったので。
でも、ここに書かれている内容は納得できます。
なるべく易しく書こう、という意図がはっきりと分かり、
そのとおり易しい言葉で書かれていると思います。
自分の知ってたことは足りない上に間違ってた事を思い知らされました。
下手に細かいコトを覚えようとするよりは、
まずこういうふうに理解すればよかったんだな、と感心しました。
入門書とはかくあるべき、と思いましたね。
お陰で、今までは得も言われぬ不安にないなまれていましたが、
この本の内容を読み返すことで、
「問題点はこういうところにあるんじゃないか」
と理解できた気がしますし、
「まだ慌てる時間じゃない。今のうちにしっかりと舵を切り直せばいいんだ」
と思えるようになりました。
気を付けたいのは、なにもこの本は、
絶対破綻なんて気のせいだ!年金最高!
と【言っているのではない】ことでしょうか。
年金擁護がどうのこうのという評もあるようですがそうではなく、
下手な情報に振り回される前に「年金とははどういうものなのか」を理解して欲しい、
という、他の著書ではおざなりになりがちなポイントにフォーカスされています。
今抱えている問題点や、それに対する議論などもある程度拾われています。
そして、どういう制度であるのかをしっかりと解説した上で、
「今すぐにも崩壊するみたいに言われるのかおかしいと思います」
と持論を展開していらっしゃる。
まずは、年金とはどういう制度なのかを理解する参考書として、
一度目を通してみるのは悪く無いと思います。
その上で他の本を読むなり何なりしてみればいいのではないでしょうか。
私は、年金というややこしそうな事を十分易しく書いてある事、
どんな問題点を抱えているかも包み隠さず書いている事、
この2点を評価して☆5つとしました。
2011年5月6日に日本でレビュー済み
この本は、深読みせずに、Q&A本として読むことをすすめる。
思想的な部分や、「〜であるべき。」という視点で読んでしまうと、価値が半減するような印象を受ける。
この本のタイトルに忠実に従うべし。
年金論になってしまうと、どうしても実用書から机上論のお披露目本に展開してしまいがち。
結局のところ、最初から年金をあてにして生きるという姿勢も疑問を持たなければいけない時期では。
日本という国が不沈であることが大前提では?
最近のメディアや、50代以降を見ていると、国家のことを論ぜず、自分には無関係だが、年金だけは他の日本人よりも巧みに受給したいという考え自体が浅はかな印象である。
思想的な部分や、「〜であるべき。」という視点で読んでしまうと、価値が半減するような印象を受ける。
この本のタイトルに忠実に従うべし。
年金論になってしまうと、どうしても実用書から机上論のお披露目本に展開してしまいがち。
結局のところ、最初から年金をあてにして生きるという姿勢も疑問を持たなければいけない時期では。
日本という国が不沈であることが大前提では?
最近のメディアや、50代以降を見ていると、国家のことを論ぜず、自分には無関係だが、年金だけは他の日本人よりも巧みに受給したいという考え自体が浅はかな印象である。
2017年10月10日に日本でレビュー済み
年金記録問題が表面化して大騒動になり、政権交代が実現し、「ミスター年金」が厚労大臣になっていた頃、
実に様々な年金問題関係の書籍が出版されていました。
本書は朝日新聞の記者が何故か文春新書から年金問題関係の書籍を出版するという意味で大変ユニークな書籍でしたけど、
当時の読後感の印象は強くはなく、そのまま本棚の奥の方に埋もれていました。
6年ぶりに改めて読み返して見ると、印象的な面白さはないけど、大筋で本質を掴んでいるというのと、
今、読んでも、極論を排するという意味で有意義な本だと思います。
この本に限らず、きちんとした視点を持った年金関係の書籍なら共通して触れていることですけど、
年金制度とは、現役世代の稼ぎを退役世代に振り替える仕組みに過ぎないのですから、現役世代の稼ぎのパイが大きくならないと、年金財政は苦しくなるのは当然の理で、
非正規雇用が増加し、現役世代の幅広い層の所得が減少傾向に陥ると、少子高齢化の構造的問題と相まって、どうにもならない訳で、
とにもかくにも現役世代の雇用安定と所得増を実現しないとどうにもなりません。
日本は島国で、(ほぼ)単一民族に近い国家なので、格差拡大化政策は決して宜しくないと改めて感じます。
実に様々な年金問題関係の書籍が出版されていました。
本書は朝日新聞の記者が何故か文春新書から年金問題関係の書籍を出版するという意味で大変ユニークな書籍でしたけど、
当時の読後感の印象は強くはなく、そのまま本棚の奥の方に埋もれていました。
6年ぶりに改めて読み返して見ると、印象的な面白さはないけど、大筋で本質を掴んでいるというのと、
今、読んでも、極論を排するという意味で有意義な本だと思います。
この本に限らず、きちんとした視点を持った年金関係の書籍なら共通して触れていることですけど、
年金制度とは、現役世代の稼ぎを退役世代に振り替える仕組みに過ぎないのですから、現役世代の稼ぎのパイが大きくならないと、年金財政は苦しくなるのは当然の理で、
非正規雇用が増加し、現役世代の幅広い層の所得が減少傾向に陥ると、少子高齢化の構造的問題と相まって、どうにもならない訳で、
とにもかくにも現役世代の雇用安定と所得増を実現しないとどうにもなりません。
日本は島国で、(ほぼ)単一民族に近い国家なので、格差拡大化政策は決して宜しくないと改めて感じます。
2011年5月12日に日本でレビュー済み
Q&A方式の年金の概説書です。
この本は、著者が新聞記者なので、新聞の解説欄のように 知識がない人を前提にしています。
そのため、漫画による解説イラストによって、大づかみの理解を得るようにしたり、掛け合い漫才のような会話形式のコラムなど、説明に非常に工夫を凝らしています。
会話式の年金雑談というコラムでは、「長妻大臣はなぜパッとしなかったのか?」という項目があり、気になっているけど、誰もが書きにくいことをズバリ書いていて、非常に面白かったです。
この会話形式のコラムには、「なぜ年金の議論は混乱するのか?」という項目があり、学習院大学の鈴木亘教授の著書「年金は本当にもらえるのか? (ちくま新書)」 との比較が出てきます。
鈴木教授の本も、Q&A方式の年金の概説書です。
ただ、著者が学者であり、経済学・財政学の視点から年金制度を捉えています。
論理、主義主張は明解で、読んでいて、経済学の観点から年金を見ると、このように見えるのかと、その切れ味に感心してしまいました。
会話の相手方(ヒヨコ)が、「鈴木教授の言っていることが、著者(クマゴロー)とあまりに違うので驚いた!」と言い、著者(クマゴロー)が、コラムの中でそれに答えています。
私の感想としては、現場の方々と直に接し、いろいろの制約の中で、苦労しながらも、何とか年金制度を良い方にもっていきたいという著者の立場の方が、現実的に思えました。
是非、両方を読んでみて、その主張の違いを体感してください。
(42)
この本は、著者が新聞記者なので、新聞の解説欄のように 知識がない人を前提にしています。
そのため、漫画による解説イラストによって、大づかみの理解を得るようにしたり、掛け合い漫才のような会話形式のコラムなど、説明に非常に工夫を凝らしています。
会話式の年金雑談というコラムでは、「長妻大臣はなぜパッとしなかったのか?」という項目があり、気になっているけど、誰もが書きにくいことをズバリ書いていて、非常に面白かったです。
この会話形式のコラムには、「なぜ年金の議論は混乱するのか?」という項目があり、学習院大学の鈴木亘教授の著書「年金は本当にもらえるのか? (ちくま新書)」 との比較が出てきます。
鈴木教授の本も、Q&A方式の年金の概説書です。
ただ、著者が学者であり、経済学・財政学の視点から年金制度を捉えています。
論理、主義主張は明解で、読んでいて、経済学の観点から年金を見ると、このように見えるのかと、その切れ味に感心してしまいました。
会話の相手方(ヒヨコ)が、「鈴木教授の言っていることが、著者(クマゴロー)とあまりに違うので驚いた!」と言い、著者(クマゴロー)が、コラムの中でそれに答えています。
私の感想としては、現場の方々と直に接し、いろいろの制約の中で、苦労しながらも、何とか年金制度を良い方にもっていきたいという著者の立場の方が、現実的に思えました。
是非、両方を読んでみて、その主張の違いを体感してください。
(42)